
2019年に映画化され、再び話題が再燃した小説『蜜蜂と遠雷』(幻冬舎文庫)。史上初の、直木賞と本屋大賞のW受賞作品でもある。本作は構想以来、約12年の歳月が費やされた。担当編集者の志儀保博さん(幻冬舎)は作家・恩田陸とどう向き合ったのか。12年間の歩みと共に、天才作家が「傑作を生むために必要なこと」に迫った。
史上初、直木賞・本屋大賞のW受賞* となった『蜜蜂と遠雷』。
約12年前のある日、それは始まった。
恩田陸さんから幻冬舎の担当編集者である志儀保博さんへの一本の電話。
「新しい作品を思いついた。タイトルは『蜜蜂と遠雷』。ピアノコンクール全体を最初から最後まで全部、書こうと思う。ついては今年、浜松で国際コンクールがあるから、取材に行きたいんだけど」
この僅かな会話が『蜜蜂と遠雷』が誕生の瞬間だった。しかし、この傑作は完成までにここから「12年間」の歳月が費やされることになる。
あまりに長く、異例だった。
文庫版『蜜蜂と遠雷』(下巻)の解説で、志儀さんはこんな舞台裏を明かしている。
「完成まで原稿料の他に、度重なるコンクールの取材費用がかかりました。発売前、予想損益を計算すると、初版1万5000部を定価1800円で販売しても1057万円の赤字。小説本の世界では、こんなことは滅多にありません」
リスクを負いながら12年間、志儀さんは何を考え続けていたのか。天才をどう支え続けたか。『蜜蜂と遠雷』誕生までの物語と共に紐解いていきたい。
*)恩田陸さんは2005年に『夜のピクニック』で第二回本屋大賞を受賞。同一作者による本屋大賞の2度目の受賞も史上初である。
『蜜蜂と遠雷』あらすじ 芳ヶ江国際ピアノコンクールに集まった若きピアニストたち。復活をかける元天才少女・亜夜。不屈の努力家・明石。信念の貴公子・マサル。そして、今は亡き“ピアノの神”が遺した異端児・風間塵。1人の異質な天才の登場により、3人の天才たちの運命が回り始める。それぞれの想いをかけ、天才たちの戦いの幕が切って落とされる。はたして、音楽の神様に愛されるのは……?ピアノコンクールを舞台に、人間の才能と運命、そして音楽を描き切った青春群像小説。
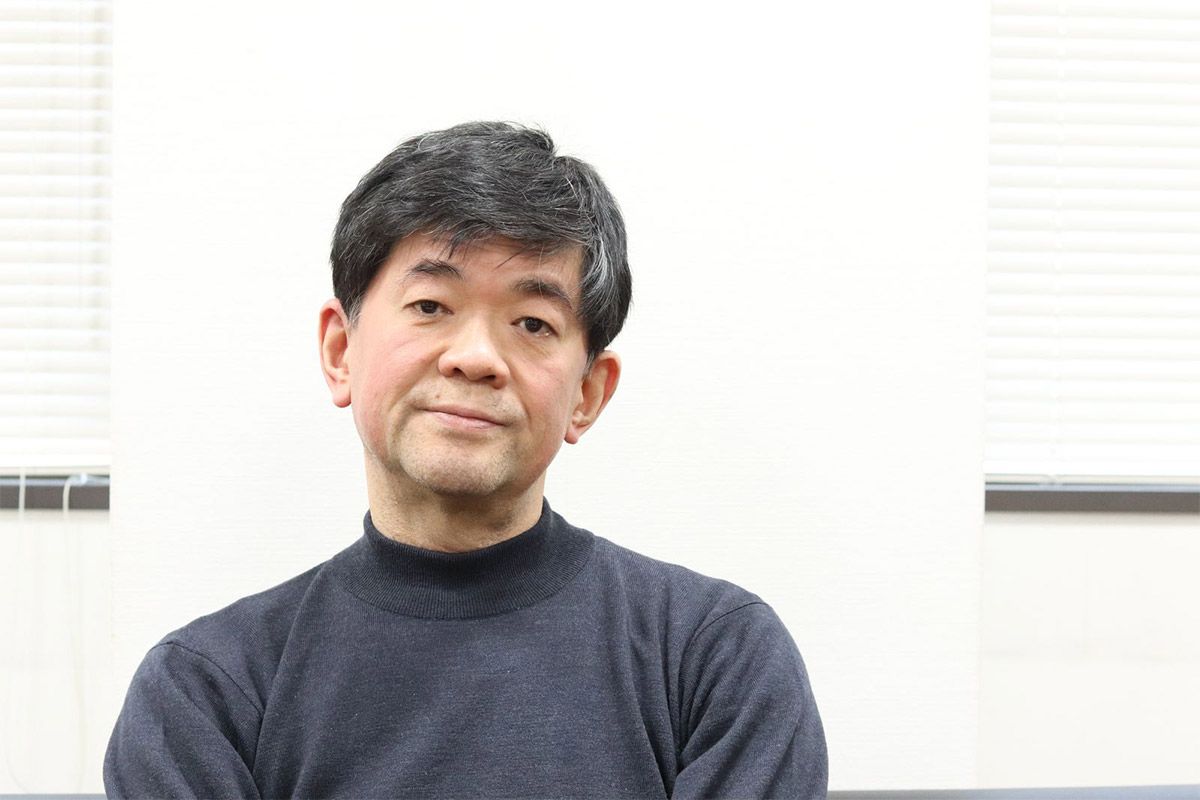
【プロフィール】志儀保博
1965年、京都市生まれ。大阪府、愛知県育ち。幻冬舎の編集者。1987年、広島大学文学部卒業、徳間書店入社。1994年、幻冬舎入社。過去の主な担当作は小林よしのり『戦争論』(1998)等。
恩田陸さんとの出会いは25年前に遡ります。当時、恩田さんは、不動産関係の会社でOLとして仕事をしながら兼業で作家としても活動していました。まだ作品数も少なく新人といってもいい時期。私は恩田さんと同い年。気心も通じやすいので担当になりました。ともに音楽好き。以来一緒にジャズやクラシックのコンサートによく行きました。
『蜜蜂と遠雷』については、12年ほど前、恩田さんから「ピアノコンクールを題材とした作品を書きたい」と電話があったんです。もともと一緒にコンサートに足を運ぶような関係だったので、私がこの作品の担当者に選ばれたのかもしれません(笑)。
ピアノコンクールって、普通に考えればマイナーな題材ですよね。甲子園の高校野球とは注目度がまったく違う。さらに歌詞のないピアノ音楽を文章で表現しなければならない。小説の技術面からいって、かなり難易度の高い作品になることは容易にわかります。けれども、作家が「やりたい」って言うとき、それは、ある程度見通しや自信があるということ。編集者として不安要素がないわけではありませんでしたが、この企画に賭けてみようと思いました。
コンクールは必ず誰かが勝ち、誰かが負けて終わる。むしろその限られた枠組みの中でどんなドラマを生み出すのか。期待が高まります。「やりましょう!」と二つ返事でOKし、浜松で行われる第6回ピアノコンクールに同行取材することにしました。
2週間のコンクールを一度取材して、すぐに執筆は開始されるものと思っていました。でも、その気配は長い間ありませんでした。ひょっとして忘れているんだろうか? 諦めたのか? 私の悶々とした日々が始まります。あっという間に2年半が経過し、でも、待ちに待った2009年3月13日朝9時に、こんなメールとともに連載第1回の原稿が届きました。
志儀様 昨日はすみませんでした。 行き詰まった上に ここんとこ二日くらい寝ていなかったので 最高に気分が悪くなり気絶。 ようやくできました。 もうデッドラインを過ぎていますでしょうが 何卒何卒宜しくおねがいします。 やはり音楽小説はむつかしいです。先が思いやられます。 恩田陸
今から思えば、その後の難産を十分に暗示しているメールです(笑)。でも、こうして、いよいよ連載開始。出だしは快調で、最初から面白い。大満足のスタートダッシュでした。
数カ月して、恩田さんから、再びコンクールを取材したい、と連絡がありました。浜松のコンクールは3年ごとなので、次の第7回がまたやってきます。「再取材したい」ということは作家が、小説を構想よりもさらに面白いものにしたい、という強い意志の現れだ、と私は自分に言い聞かせて、またもや2週間の取材に同行しました。
恩田さんは連載開始以来、会うたびにずっと「書けない」と口にしていました。「うーん、とにかく書けない」と何度も何度も。音楽を文章で表現するというハードルが、作家の想像を超えた高さだったんだと思います。
今ではいい思い出話ですが、「書けない」恩田さんと何度も交わした会話があります。恩田さんが「風間塵(※)を2次予選で敗退させる」と言うのです。3次予選の時もそう言ってたな(笑)。私はただ「ありえないでしょ」と返事しましたが、内心それだけは絶対に避けたい、と冷や冷やしていました。ただ、それくらいこの作品を紡ぎ続けることは困難で苦しいのだ、ということはよくわかりました。
※風間塵…本作における主要人物の1人
中盤になって「本選、書くのやめようかな」と言ったこともありますね。私は「絶対にだめです」と言いつづけました。
これらは、どこまで本気だったのかわかりませんが、とにかく書くことが苦しいから一人でも敗退させたいし、選考過程を1つでも省きたい。その気持ちは手に取るようにわかりました。
でも、もし主要人物がいなくなったら作品の完成度が下がることは目に見えている。コンクールのすべてを書くという大いなる挑戦が目論見から遠ざかる。宥めるように励ますしかありませんでした。
誰よりも近くで天才作家が苦しむ姿を見て共感しながら、原稿の催促を過酷に続ける。そんな日々が7年近く続きました。
少しずつ連載原稿を積み重ねる間に12年の月日が流れました。浜松国際ピアノコンクールの取材は合計4度に及び、ほぼすべての日程、会場に足を運びました。朝9時から夕方の6時までひたすら客席中央で演奏を聴き続けます。裏方のスタッフ、調律師などへは一切取材することなく、ただただ演奏だけを聴き続けました。
私もずっと恩田さんの隣で聴いていました。演奏を聴きながら恩田さんがストーリーの展開を閃いた様子は感じられませんでした。ひたすら「ピアノの音を言葉にするとは、どういうことなのか」の自問自答を繰り返していたのだと思います。
私は『蜜蜂と遠雷』の完成まで、恩田さんの要望にはできるだけ応えたいと思っていました。断ったことは多分、一度もありません。
有名ピアニストのコンサートにも行きました。しょっちゅう飲みにも行きました。その回数は100や200回じゃきかないと思います。クリエイターには後悔のない作品を生み出してもらいたい。
ただ、積み上がった取材、その他にかかる「諸経費」はこれまでに見たことのない額に膨れ上がっていました。
初版1万5000部が売れても赤字は1000万を超える状況でした。幻冬舎の部数決定会議でそれを社長である見城徹に伝えなければなりませんでした。叱られるのは必至、もしかしたらクビになるかもしれない。それほど異例のことでした。ただ、見城に、正直に経費の説明をすると意外な答えが返ってきたました。「あ、そう」と一言だけ。こうして『蜜蜂と遠雷』は、2016年9月末に発売されました。
単行本が店頭に並ぶと、最初から比較的よく売れました。書評や紹介記事もたくさん書かれ評判も上々でした。そして2016年12月、直木賞の候補にノミネートされたと連絡がありました。そこから受賞決定までの1ヶ月間は落ち着かない日々が続きました。
恩田さんは「私は運が悪いから直木賞、取れない気がする。もう5回も落ちてるし。だから志儀さんの運に賭ける」と言っていました。私は「取れますって! 俺は運がいいから」と。
口ではそう言っていたけど、内心は不安もありました。もし、落選したら、どんな言葉を掛けるか。そんなことばかりが、頭の中を巡っていました。
だから受賞の報せが届いた時は、ただただ安堵しました。受賞直後から怒涛の勢いで取材依頼が舞い込み、1ヶ月半の記憶がほとんどありません。
その後も直木賞と本屋大賞の贈呈式、映画化やアニメ化の内定やコンサート化など、いろんなイベントが決まり、慌ただしい日々が続きました。
なにより私がうれしかったのは、12年間を掛けて紡いだ『蜜蜂と遠雷』が、恩田さんにとって後悔のない作品に仕上がったことと、それに最後まで伴走できたことです。

振り返ってみて、私自身が『蜜蜂と遠雷』と向き合うなかで、いくつか大切にしてきたことがありました。
まずは作家の邪魔をしないこと。特に恩田さんのようにすでに何冊作品を持ち代表作もある作家は「見守る」に徹します。
ただ、新人作家にはダメ出しをしたほうがいいこともあります。たとえば、「変なクセ」は早く矯正したほうがいい。わざと「雑味」を入れているものはいいのですが、読者に嫌悪感しか与えないような書きぶりは強く指摘しなければなりません。
一方で「個性」はちゃんと伸ばしたい。逆に表面的には綺麗だけど、個性がない作品、うまく終わっているだけの作品はどうしようもありません。どこか変なんだけど、それが魅力的で、しかもメジャーに通じる回路を持っている、そんな新人の作品を待っているし、その誕生に付き合いたい。ないものねだりに聞こえそうですが。
たとえば、歌手の声でいえば、J-POPなら中島みゆき、ユーミン、椎名林檎…みなさん、かなり「異質な声」をお持ちだと思います。「透き通った、きれいな声」はどうしても印象に残りづらい。必ずしも歌が上手くなくても独特であるほうがいい。それが個性ですよね。これは小説でも同じだと思うのです。
作家は、書きたいものが常に決まっています。そして「これを書かないと次の作品に進めない」それが作家というものです。小説を書かずにはいられないから作家なわけです。書きたいものを出しつづけた先に、ある時、運命的に大傑作が生まれるのだと思います。
その時、編集者は何ができるのか。
天才が傑作を作ろうとしているのですから、支える者としては「狂った勇気」を持ち続けなければならない。『蜜蜂と遠雷』でいえば、こんなにお金を使っちゃってるけど「まあ、しょうがない。傑作だもの」と思うことにしました。
売れなければクビになったとしても、会社に叱られたとしても、それでも「世に出す勇気」があるか。クリエイターとその作品を信じ抜く「勇気」が編集者にはいちばん必要ですね。
4月から新社会人となるみなさんに、仕事にとって大切なこと、役立つ体験談などをお届けします。どんなに活躍している人もはじめはみんな新人。新たなスタートラインに立つ時、壁にぶつかったとき、ぜひこれらの記事を参考にしてみてください!
経営者たちの「現在に至るまでの困難=ハードシングス」をテーマにした連載特集。HARD THINGS STORY(リーダーたちの迷いと決断)と題し、経営者たちが経験したさまざまな壁、困難、そして試練に迫ります。
Notionナシでは生きられない!そんなNotionを愛する人々、チームのケースをお届け。